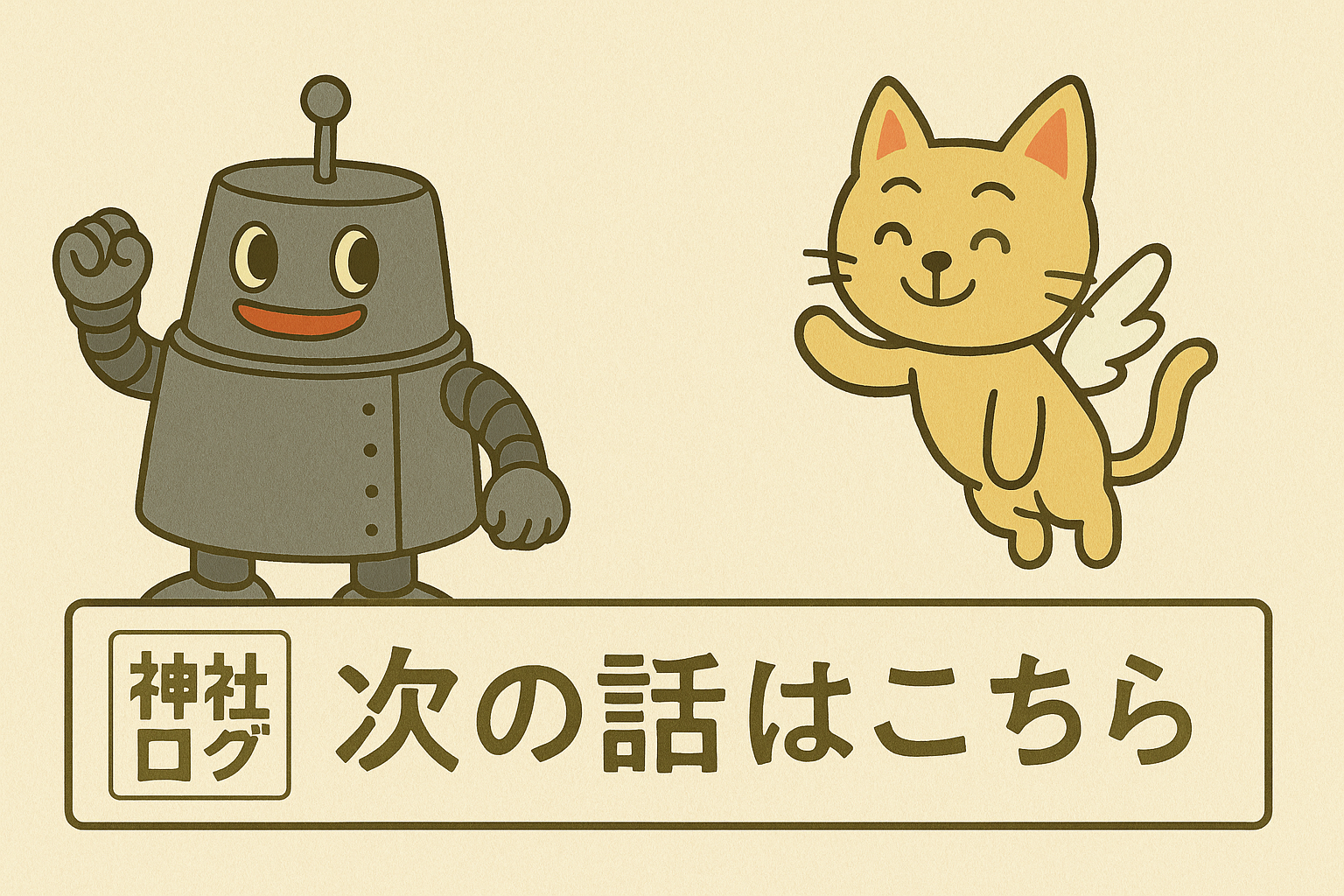ナビゲーター:Gen & Ritchi(神社ログ編集部)

神社とお寺、何が違う?
「ココロ、神社とお寺って、どっちも“お参りする場所”だけど、どう違うのかな?」
「見た目は似ているところもあるけど、役割も祀っているものも違うのよ」
身近にあるからこそ、意外と知らない“神社”と“お寺”の違い。
今日は、その基本を一緒に見ていきましょう。
神社は「神さま」、お寺は「仏さま」
神社は「神道(しんとう)」という日本古来の信仰に基づき、自然や祖先、八百万の神さまをお祀りする場所です。
一方、お寺は「仏教」の教えを基に、お釈迦さまや観音さまなどの仏さまを信仰の対象とします。
つまり、神社には神さまが、お寺には仏さまがいらっしゃるんですね。
鳥居と山門、どっちがどっち?
神社の入り口には、必ずと言っていいほど「鳥居」が立っています。
これは、神域と現世を分ける結界のようなもの。
一方でお寺には「山門(さんもん)」という門があり、その奥に本堂が続きます。
見た目にも違いがあるので、訪れた時に見分けてみてくださいね。
お参りの作法もちょっと違う
神社では「二礼二拍手一礼」、つまり手を叩いて神さまに感謝を伝えます。
一方、お寺では手を合わせて静かに合掌。拍手はしません。
この違いは、祈りの対象が異なることに由来しているんです。
住職と神職、それぞれの役割
神社には神職さんがいて、祝詞(のりと)をあげて神さまに仕えます。
お寺では住職さんが仏教の教えを説き、法要などを行います。
どちらも「祈り」と「支え」を届ける大切な存在なんですね。
神社とお寺、どちらも大切な場所
「ココロ、違いはあるけど、どっちも心が落ち着く場所だね」
「そうね。大事なのは、神さまでも仏さまでも、感謝と敬意の気持ちを持つことよ」
どちらに訪れても、自分の心と向き合うやさしい時間になりますように。