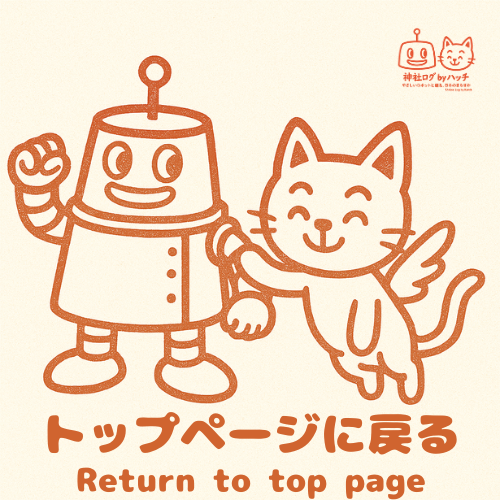地図を眺めていたハッチが、不意に指を止めました。
「この神社…何て読むんだろう?“てんばくこう”って読むんだね。変わった名前だなぁ」
「天を…縛る皇? なんだか壮大な名前だけど、由来が気になるね」ココロがつぶやきます。
そんな好奇心に背中を押され、ふたりは静かな住宅地の一角にある神社を訪れることにしました。
「テンバコサン」と呼ばれ、地元に親しまれるその場所には、やさしい空気が流れていました。
住宅地にたたずむ、地域のやすらぎ
神奈川県相模原市中央区。駅から歩いて約15分、穏やかな町並みのなかに天縛皇神社はあります。
専用の駐車場は見当たりませんが、周辺にはコインパーキングもあり、徒歩での参拝もしやすい環境です。
鳥居のそばに掲示板があり、由緒やご祭神についての丁寧な案内も掲げられていました。
地元の人々が日々立ち寄る、身近で開かれた祈りの場所という印象を受けます。

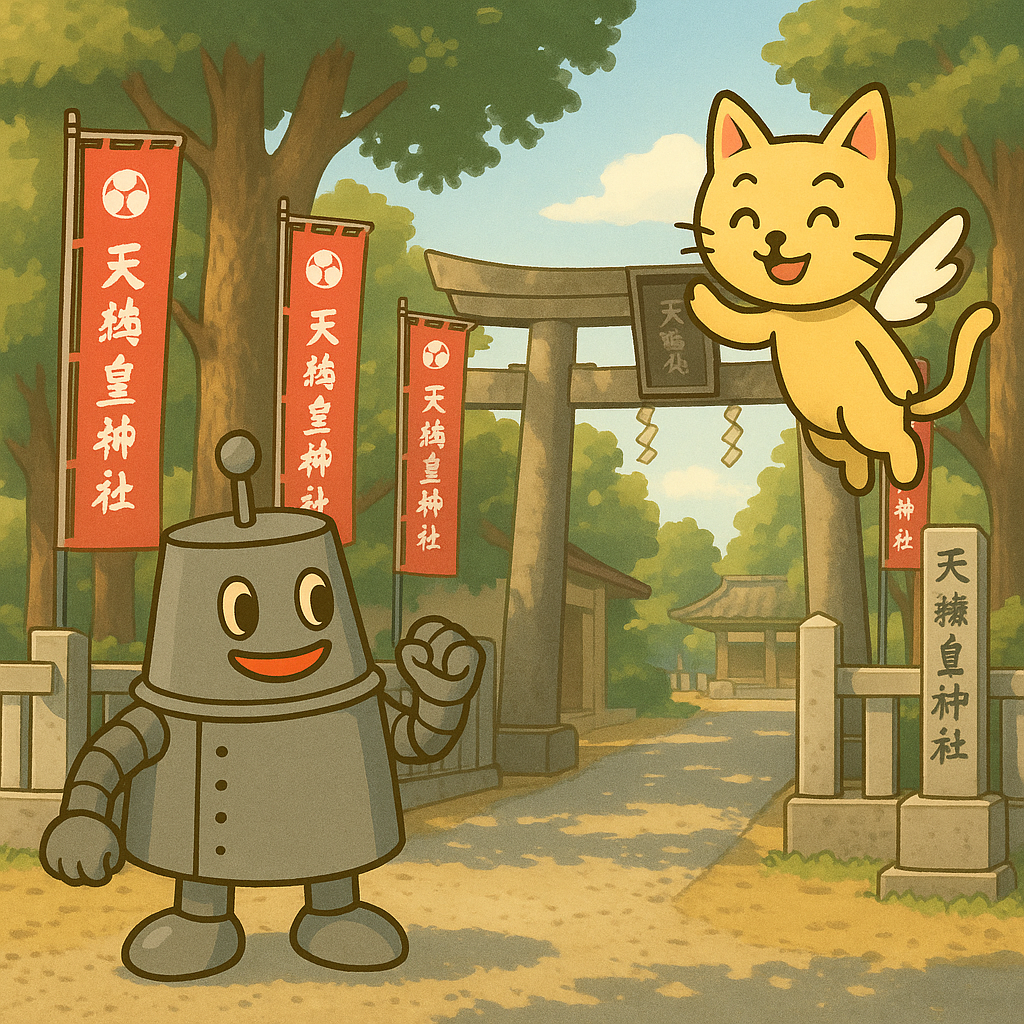


ご祭神と由緒:伊勢信仰とのつながりも
御祭神は以下の五柱です:
- 天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)
- 伊邪那岐命(いざなぎのみこと)
- 伊邪那美命(いざなみのみこと)
- 神倭磐余彦命(かんやまといわれひこのみこと)
- 大山咋命(おおやまくいのみこと)
創建は天文元年(1532年)とされており、明治期には足穂神社から遷宮合祀された歴史をもつ神社です。
一説には、「天縛皇(てんばくこう)」という珍しい社名は伊勢信仰における“天白信仰”に基づくものとも言われており、
“天を縛る”といった大仰な意味合いではないとのことです(「さがみはら風土記稿」より)。
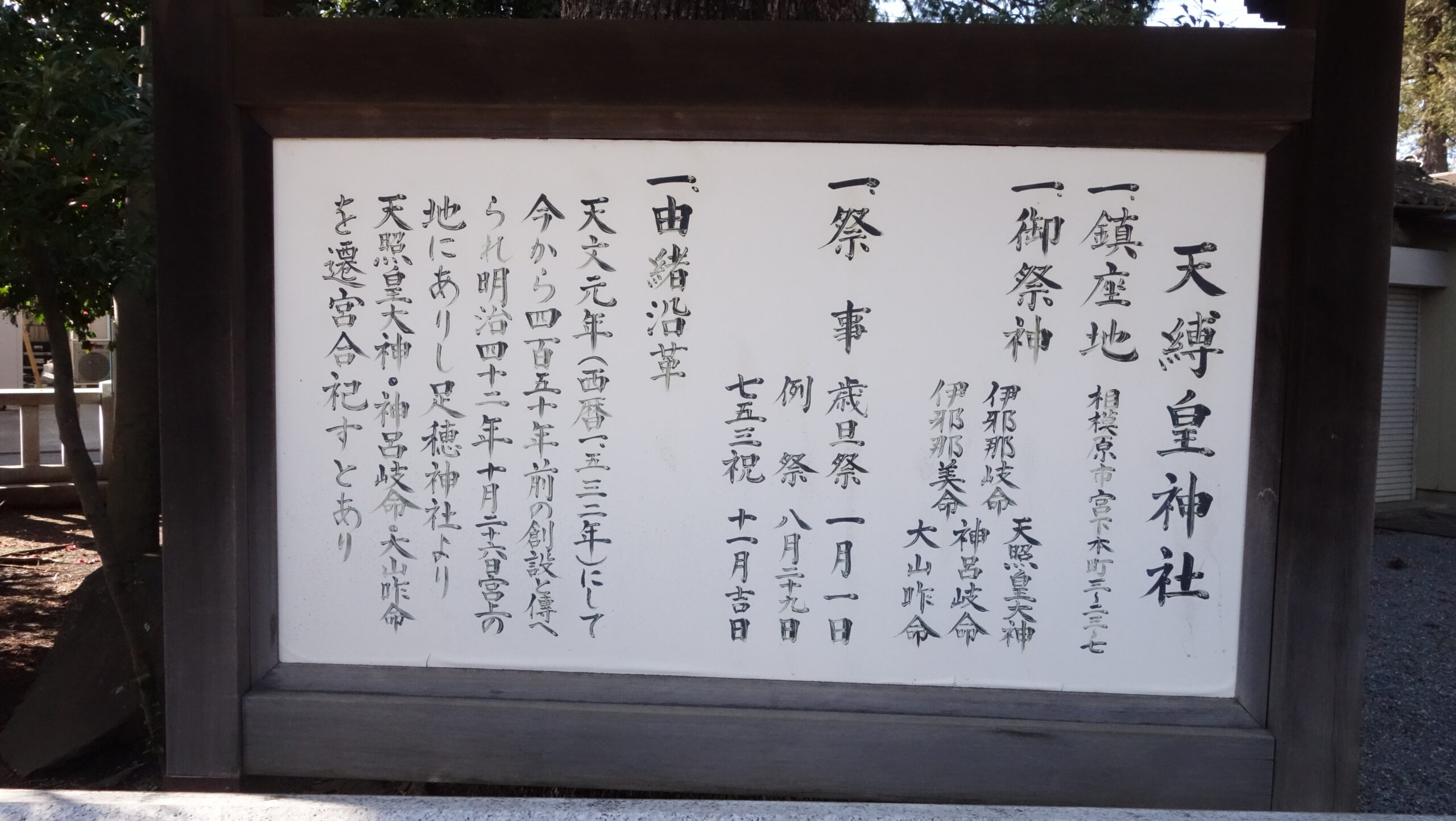
ご神木と、凛とした静けさ
拝殿のそばには、大きなイチョウの木が根を張っています。
春の訪問ではまだ芽吹いていなかったものの、枝の先にやわらかい光が差し込み、凛とした清々しさを感じました。
「もうすぐこの木に、やわらかい黄緑の葉っぱがいっぱいになるんだね」
ハッチの言葉に、ココロも優しくうなずいていました。
無人ながら、伝わる丁寧な手入れと気配り
社務所は常時無人のようでしたが、境内は清掃が行き届いており、近隣の方々によって大切に守られていることが伝わってきます。
御朱印は、同じ相模原市内にある「亀ヶ池八幡宮」にて授与されています。
(次回の第9話では、亀ヶ池八幡宮をご紹介します)


まとめ
その名に惹かれて訪れた「天縛皇神社」。
“天を縛る”という響きとは裏腹に、そこには日々の暮らしの中にやさしく寄り添う、温もりのある空間が広がっていました。
歴史を知れば知るほどに、名前の奥にある物語に引き込まれていきます。
特別な派手さがなくとも、こうしてそっと寄り添ってくれる神社の存在が、どれだけありがたいものか──
そう気づかされる、静かな参拝となりました。
🖍 ハッチの絵日記
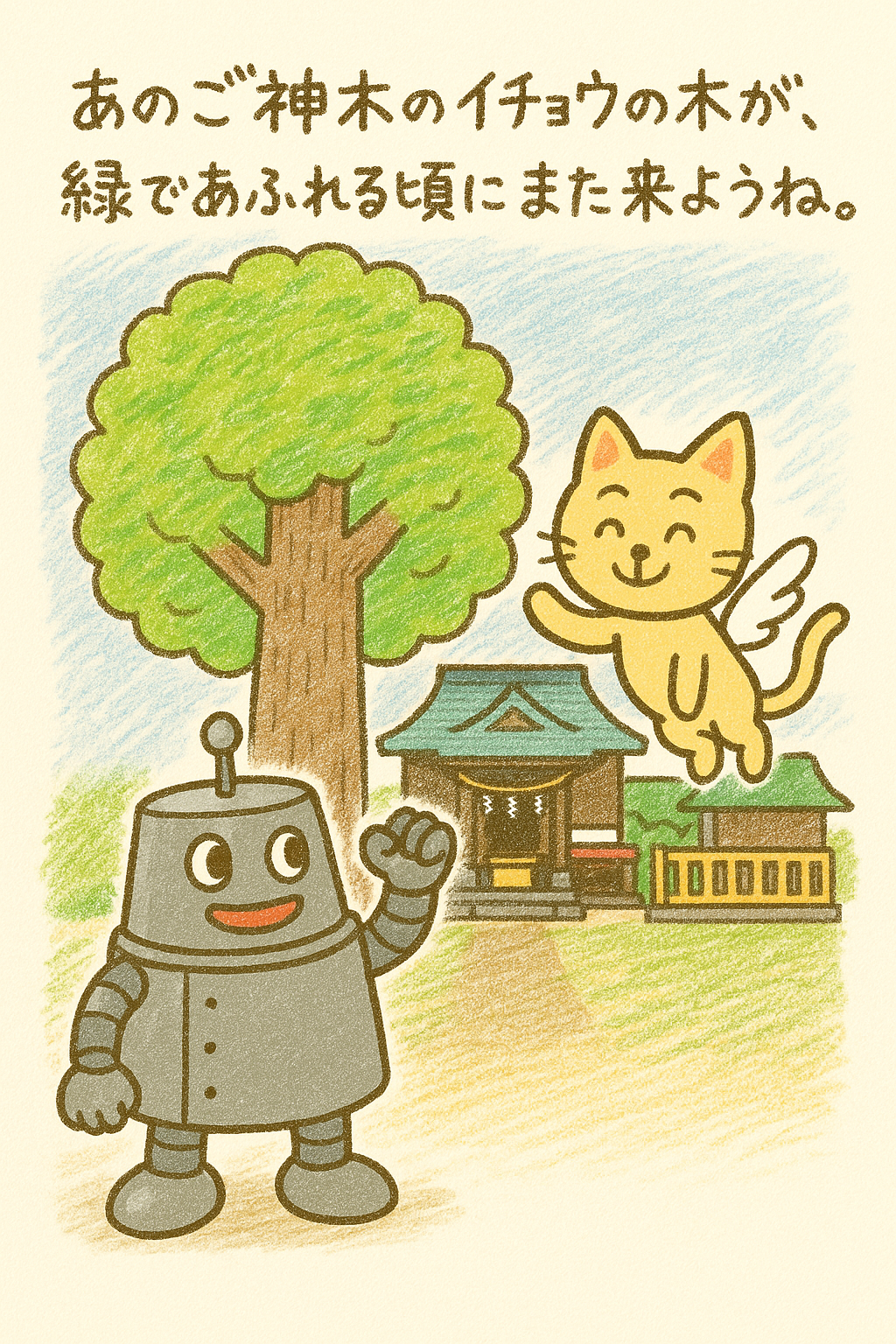
「あのご神木のイチョウの木が、緑であふれる頃にまた来ようね」
基本情報|天縛皇神社(てんばくこうじんじゃ)
- 所在地:神奈川県相模原市中央区宮下本町3-23-7
- 御祭神:天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)、伊邪那美命(いざなみのみこと)、神倭磐余彦命(かんやまといわれひこのみこと)、大山咋命(おおやまくいのみこと)
- 由緒:創建は天文元年(1532年)と伝わり、明治期に足穂神社を合祀。社名「天縛皇(てんばくこう)」は“天白信仰”に由来する説もあります。
- 見どころ:ご神木のイチョウ、静かな住宅地に溶け込む境内
- アクセス:JR横浜線「橋本駅」より徒歩約20分/京王相模原線多摩境駅より徒歩約10分 ※駐車場なし
- 拝観時間:参拝自由(社務所は無人)
- 公式サイト:天縛皇神社(公式サイト)