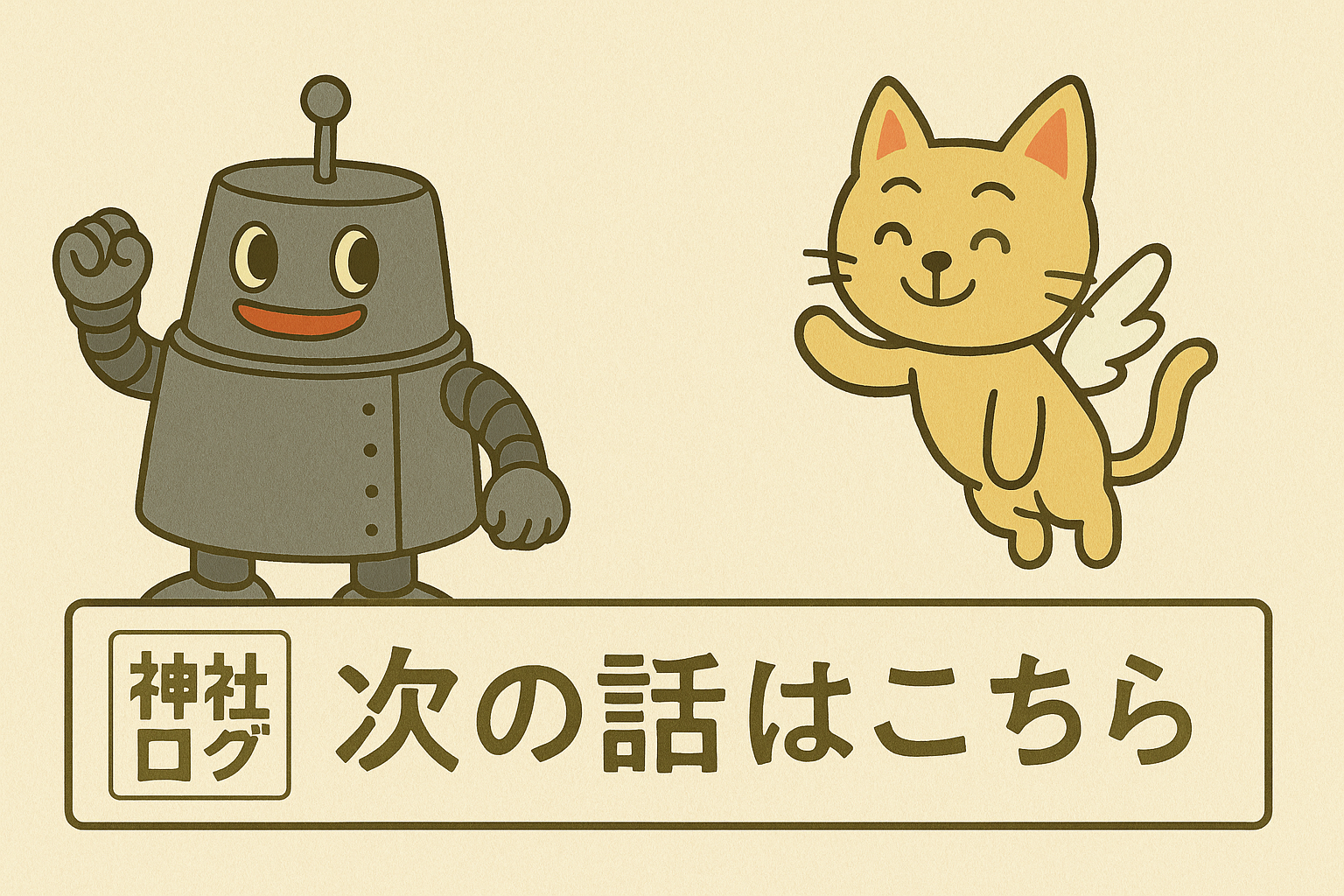ナビゲーター:Gen & Ritchi(神社ログ編集部)
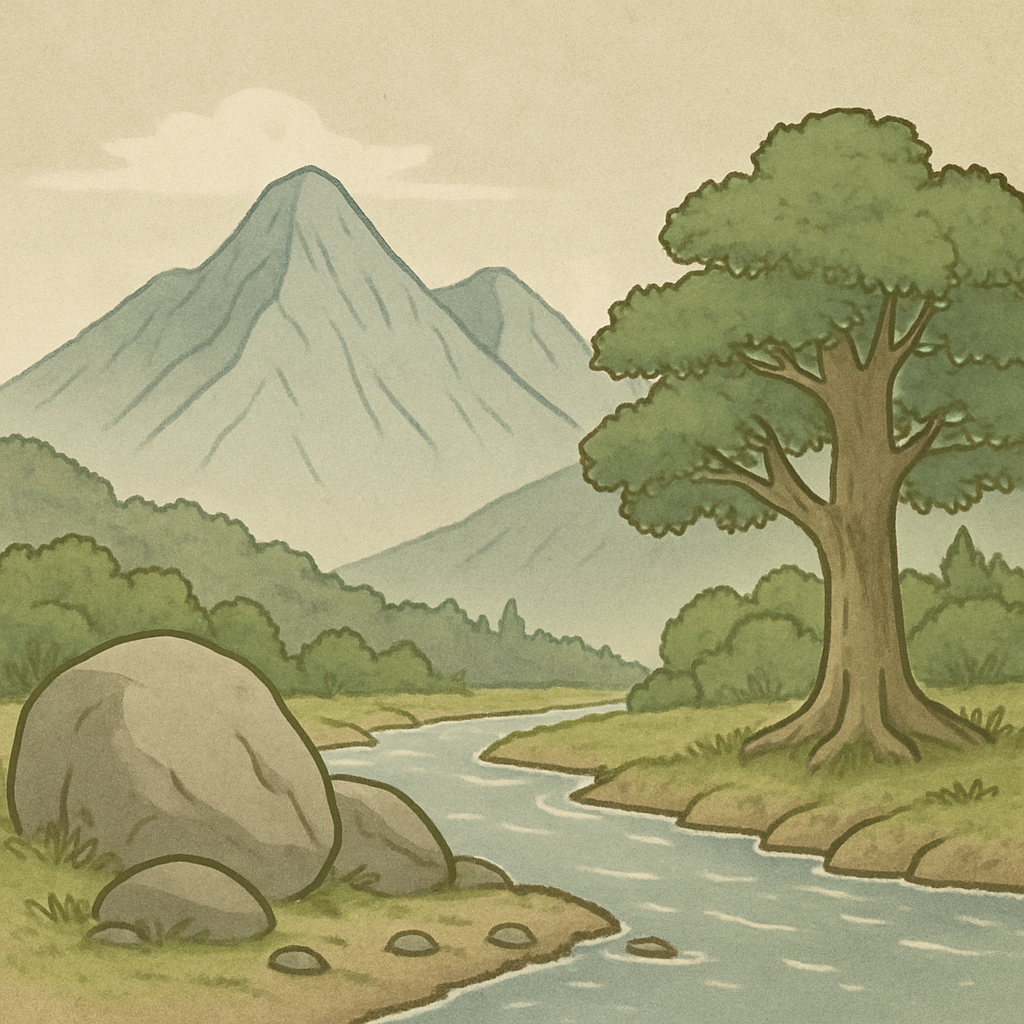
ハッチ: ねえ、ココロ。神社って、いったいいつごろから存在しているんだろう?
ココロ: そうね。昔は神社という建物はなくて、人々は山や大木、大きな岩などの、自然そのものを神様として信仰していたみたいよ。
神社は、どこから来たの?
「神社」って、いったい何なのでしょう。
昔から日本にあった? 誰かがつくった?
その答えは、自然とともに暮らしてきた日本人の“こころの形”の中にあります。
神社のルーツは「自然そのもの」
神社のはじまりは、今のような建物ではなく、山や森、岩や滝などを神聖な場所とする「自然信仰」でした。
古代の人々は、大きな山に神の気配を感じ、豊かな森や湧き水に神の存在を見いだしていたのです。
「やしろ」は、祈りの場をつくることから
やがて、人々は祈りの目印としてしめ縄や鳥居を設けるようになります。
それが少しずつ「やしろ(社)」という形になり、現在の神社建築の原型となっていきました。
つまり、建物が先にあったのではなく、祈りの心が先にあったのです。
神様は「まつる」もの
神社の役割は、神様を“まつる”=敬い、感謝を捧げること。
この“まつり”の文化が、神事(しんじ)やお祭り(例祭)として今も受け継がれています。
地域によってまつる神様や風習が違うのも、その土地ごとの歴史や自然への思いが込められているからです。
山・海・空も「ご神体」
伊勢神宮では「山」が、長野の諏訪大社では「湖」や「風」がご神体とされています。
このように、自然そのものが神様として祀られている神社も数多くあります。
神道は、自然と人が共に生きるという世界観から生まれた信仰なのです。
ハッチ: 神社って建物じゃなくて、心のあり方なんだね。
ココロ: そう。見えないものを大切にする気持ちが、やしろの形になったのよ。
ハッチ: じゃあ、次に神社を訪れたら、周りの山や木も、ちゃんと見てみるよ。